2011年06月24日
島田の散歩
島田の建物の散歩をしました。みのる座、萬露亭、北川製品所、児玉邸、天徳寺でした。みのる座は解体中、萬露亭の庭池の石橋:大きな岩の組み方、庭に面したガラス戸:鉛ガラスの歪み、北川製品所の研究所?:20世紀初頭のウィトゲンシュタイン又はアドルフ・ロース風、同じく木造の軒下:学校または幼稚園の軒下。工場の妻面:ブルックリンの裏街風、児玉邸玄関、児玉邸縁側:外側に向けて勾配。天徳寺:日本建築は軒裏が語る。







フェルナン・プイヨンの「粗い石」は現在真ん中を過ぎたあたりで、難解な記述(日本語だけど)です。でもスゲーって感じで、気迫が現代とは違う。と思ったけど、今でもこのような人が居るのかもしれない。私が気づいていないのかも、すぐ近くに居たりして?情熱の時代は去ってしまったのか?見えなくなってしまったのか?情熱はカッコ悪くないし。情熱が無ければこれらの建物も出来なかった筈。これからも必要だよ。情熱こそが明日を変えられるんだ。って自分に言い聞かせながら。ミスチル風
フェルナン・プイヨンの「粗い石」は現在真ん中を過ぎたあたりで、難解な記述(日本語だけど)です。でもスゲーって感じで、気迫が現代とは違う。と思ったけど、今でもこのような人が居るのかもしれない。私が気づいていないのかも、すぐ近くに居たりして?情熱の時代は去ってしまったのか?見えなくなってしまったのか?情熱はカッコ悪くないし。情熱が無ければこれらの建物も出来なかった筈。これからも必要だよ。情熱こそが明日を変えられるんだ。って自分に言い聞かせながら。ミスチル風
Posted by 新茶 at
14:45
│Comments(3)
2011年06月17日
座敷わらし
「愛しの座敷わらし」萩原浩:著 朝日新聞出版です。ポピュラリティー(単純で解かり易いく、万人受けする)のある物語です。純粋な人間だけが見える座敷わらし。せっかちで風潮に流されやすく、個人主義と利己主義を混同している現代人への批判でしょう。日本の心が日本人の一家を救い始める物語でした。ジワーと涙ものです。またしても写真がピンボケです。座敷わらしのしわざでしょう。私の横にはいつも座敷わらしがシャツを掴んで立っていますよ。見える人だけに見えるのだ。文庫本も出ているのかな?「百年前の少女」も良かったね。懐古趣味って云われそうです。これからフェルナン・プイヨンの「粗い石」を読む予定です。これまたフランスですが中世の物語?です。知ってる人は知ってるんだろうねトロネだよ、ロマネスクだよーん。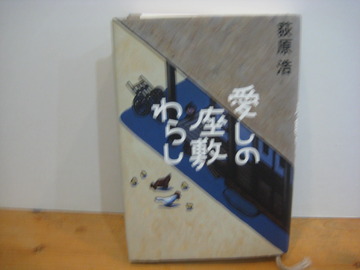
Posted by 新茶 at
09:46
│Comments(2)
2011年06月12日
ジョサイア・コンドル
「暁英」贋説・鹿鳴館 北森鴻 著(徳間文庫)を読みました。以前この作家のことを書きましたが亡くなりましたので未完の作品です。とてもよくこの時代背景が描かれています。日本が背伸びをしなければならなかったこと、建築家と社会の絡みなども含めて、未完ながら感動させられました。コンドルの弟子たち、辰野金吾、片山東熊、曾禰達蔵、左立七次郎ももちろん出てきます。肝心な人物、井上馨、反骨の画家河鍋暁斎が鍵を握っています。建築史もこんな風に勉強したら面白いなって思いました。なお東熊の読みを私はカタイって習ったような気がするんだけど、はっきりトウクマと書いてあります。暁斎の読みもキョウサイです。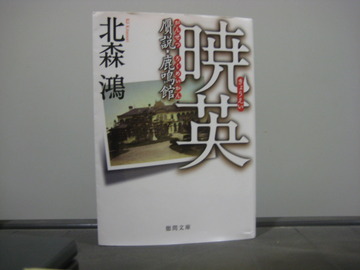
Posted by 新茶 at
21:06
│Comments(0)
2011年06月11日
反原発?
要するに何も知らない訳です。知らないで容認している私だったわけですが、今になって、少しづつ知り始めたのです。空港のときもそうです。ムード(空気)で「よろしいのかもね」って進んでしまうのですね。ある空気を作ればそれにまきこまれて一緒に流されていくんですね。それに目の前の金は大きな誘惑だもんね。逆に今、反原発の空気も流れています。社会がある空気に蔓延されたときに異論を語るのは、とても勇気や覚悟が必要です。今回確かに原発はリスクの多い装置であることを知りました。一度失敗すると取り返しの効かない科学の産物です。人間の力、科学の力は絶対的だろうと信じる人は居ませんが、賢い人がやっているのだから間違いなど無いだろうと思っていたのは確かです。エネルギー消費に安穏とした観念で日々過ごしていたわけですね。電力会社にしても可能な限り(法律上の、建て前上の)情報は公開していたのでしょう。今のこの生活を維持していくための方策だったのでしょう。これまでの経過は自分たちが、皆で是認してきた結果だと思うのです(空気で流されていたとはいえ)。黙り始めることが恐ろしい事の始まりなのでしょう。知らなければいけないことや、知らせなければいけないことが、とてつもなく多くなりました。民主主義ってすごい難しいことなんですね。元に戻って、自転車レベルの文明に戻れるのかな。私の憧れは中世の牧歌的景色です(少しの経済で生きて行けそうだし時間が掛かってもそんなもんだって思えてしまえる)。ブログだからグダグダ書いてきましたが、結論はまだまだです。ゴロっと変わるかもね。
Posted by 新茶 at
10:58
│Comments(0)
2011年06月07日
ハイク
俳句ではなくてハイキングです。①清見寺の内外緩衝空間、庭から玉座に至る空間に様々なヒエラルキーが具体的な堺目をもたずに連続する和空間。和式幾何学が自然と融合する。②分離派っぽい橋、地方に行くとたまに分離派っぽいのってあるね。近代的でおしゃれだった。③薩捶峠の絵、富士山があると具体的すぎる。見えない富士をイメージするのです。日本画ってすごいね。④海と空の境目、杉本博司風の写真のつもり。まねばっかりしている。⑤休みの日の午後、「いやでも明日はくる。」悶々、「でもきっといつかは」勝手にシナリオ作ります。⑥傾斜地の洋館公会堂、画面の中の線だけ抜き出したら、美しい。「洋館ぽくするのは進歩の象徴」今も変わらないね。本物でなくていいんだ。本物なんて何処にもないよ。自分が本物。





Posted by 新茶 at
09:40
│Comments(2)
2011年06月01日
宮部みゆき
「ばんば憑き」読みました。宮部の時代物は本当にいい。とぼけた人間ばかりで、肩が凝らない。でもジーンとくる。こんなで人間はいいんだよね。神も仏も物の怪も人間も、みーんないい。とにかく心が温まる。でもね本当は「じっくり考えること」を云っているような気がする。ただそのときの感情でものを云ったり行動することをしちゃあだめだよってね。左脳も働かせるんだよってね。作家ってみんなその様な事を言うために書いているんじゃないかな。って思いました。近頃写真を撮らないので寂しい。そのうち自画像でも載せてみようか。気持ち悪いかな。
Posted by 新茶 at
21:54
│Comments(4)

